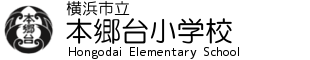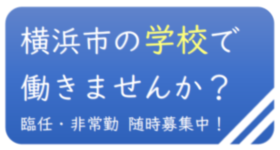★ちょっと難しい避難訓練
R7.1月9日(木)
みなさんこんにちは。昼間は日差しがあって温かかったですが、陽がかげるとても寒いですね。インフルエンザの罹患数が横浜市でもかなり増えてるそうです。15歳以下が多い(全体の55.5%)のが今冬の特徴だそうです。大人も子どもも、手洗いうがいでしっかり予防しましょうね。
さて、今日は、今年初めての避難訓練の様子をお伝えします。今日は地震が来た後に火災が発生する、しかも予告なしの訓練、+、最初の地震の後に停電で放送が使えない、というなかなか難しい設定の訓練を行いました。事前学習として、地震と火事の時の避難について指導していましたが、本日、どのタイミングで地震が起こるのか、どこで火事が起こるかは予告はしていません。はじめの地震の時は、子どもたちは落ち着いて静かに机の下に避難しました。これまでの訓練の成果がちゃんと身に付いています。学年主任が学年の子どもの様子を伝えに本部の職員室に報告に来るのですが、その時、地震による倒壊や破損で通れないところがないかを確認しながら来るのですが、その報告を聞いて避難経路を決定します。学年主任が学年のところに戻る途中、火災を発見し、本部や近くにいる職員で初期消火を行いました。放送が使えないので、火事が起きていることを本部にいる職員が大きな声で手分けして子どもと担任に伝達に走りました。今日の火事は2階奥、生活科室前、という想定で行いました。ここは非常階段の出入り口があるところなので、非常階段と緑階段が使えないことになります。初期消火で火は消したものの避難経路にその二つの階段が使えないことも情報として伝えなければなりません。この辺りの職員の動きと伝達が非常に難しかったです。次々に起こる事態に即判断を下し、子どもたちを安全なところに避難させるのですが、今日のように、あえて難しい設定をすることで、いざという時に状況判断し、行動することができるようになるのだと思います。子どもたちの訓練でもあり、大人の訓練でもあります。
校庭に避難したとき、初めは校庭の真ん中よりに避難していましたが、発災場所が生活科室(キッズの上にある部屋です)なので、なるべく遠くにということで移動を行い、火元からなるべく遠いところに避難することができました。えらいなあと思ったのは、校庭の砂場のところ二ある門から消防車が入ってくるのですが、ちゃんと消防車が入る動線を考え、そのスペースを空けて自分たちの避難場所を考えた子ども達です。前回の火災の訓練で学習したことでした。
難しい訓練でしたが、子どもたちは落ち着いて行動することができました。大人もしっかり考えて行動できるように頑張りまし。でも課題はいろいろです。防災についての研修では、避難訓練は、予定調和通りやるのではなく、毎回課題を見つけられることが大事、ということを教わっています。それが様々な状況を判断する力につながる、ということでした。一人ひとりが命を守る行動をとれるよう考えること、そしてみんなで命を守り合えるように協力しながら行動すること、そういう気持ちと行動力を、全校で、継続して育てていきたいと思います。