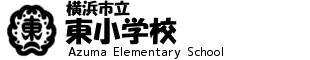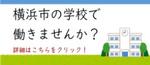【専任だより】東小学校の歴史を学ぼう
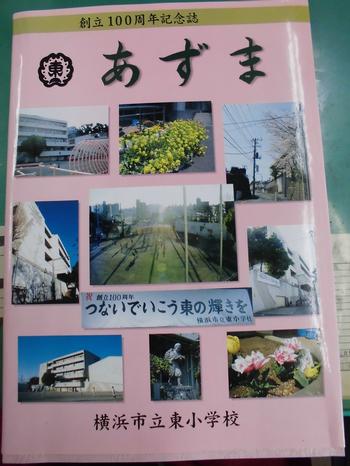
今日からちょうど1か月前の4月11日、東小学校は115回目の誕生日を迎えました。
例年は体育館で誕生日をお祝いしますが、今年はホームページで歴史の一部を紹介します。
江戸時代、今の西区は東海道に面していて江戸(東京)との交流も盛んでした。
また、神奈川奉行所もあり、学者などが出入りして教育の盛んな場所でした。
横浜の開港後は外国語を学ぶ必要もあり、外国人の先生が教える高島学校という横浜で最初の小学校もできました。
明治時代になり、「小学校令」が出され、小学校が義務教育になりました。このころは6歳から14歳までの間に4年間の教育を受ける仕組みでした。
この時期には伊勢佐木・末吉・若葉町の子どもは吉田小学校に、日の出・黄金・初音・赤門・英町の子どもは太田小学校に通っていました。
その後日露戦争(ロシアとの戦争)の後、義務教育が6年になり今の南吉田小学校の場所に「横浜市立第2高等小学校」ができました。この開校式が行われたのが明治38年(1905年)4月11日でした。この日を東小学校の誕生日にしています。
その後、大正12年(1923年)の関東大震災の後、地震に強い建物を作ろうとレンゲの咲いていた原っぱであった今の場所に鉄筋コンクリートの学校ができ、引っ越してきました。
その際に「東尋常高等小学校」と名前が変わりました。
東小学校の歴史の前半部分を『創立100周年記念誌 あずま』からまとめてみました。
ほんの一部ですが歴史を調べることによって新たに疑問が出てきたり、今までの見方が変わったりすることがありました。
そのことが勉強することの楽しさだと思います。
歴史を調べるには本などの資料を使うことももちろんですが、地域の方や家族などの卒業生に話を聞くこともできます。ぜひ、この楽しさを感じてもらい、新しくわかったことがあれば学校再開後に先生にも教えてください。