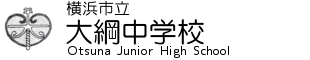令和7年度 校長所懐
校長所懐 令和8年1月
干支(えと)とはうまくいったもので、「あなたの干支は何ですか?」という質問に正しく答えられる人がどれだけいるだろう。たいていの人は、「とら年」や「うさぎ年」などと答える。これは、干支ではなく「十二支」である。一般に「ね・うし・とら・う・たつ・み・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・い」という言い方で知られる。「うし」や「とら」、「うま」や「ひつじ」など誰もがイメージしやすい動物もいれば、「ね、う、み、い」などの一文字は何の動物かわかりにくい。さらには、「たつ」のように想像上の生き物もある。「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」と漢字で書くとわかりやすくなるものもあるが、「子」や「卯」は依然わかりにくいままである。「子」はねずみ、「卯」はうさぎと言い換えてやっとわかる。いずれにしてもこれは十二支であって、干支ではない。干支は、これに「甲乙丙丁戊己庚辛壬癸」の十干が組み合わされる。同じねずみ年でも、「甲子きのえね」「丙子ひのえね」「戊子つちのえね」「庚子かのえね」「壬子みずのえね」と5種の干支がある。つまり、全部で60種類の干支があることになる。
中学生の皆さんなら、「とら年」「うさぎ年」「たつ年」「へび年」なので、「庚寅」「辛卯」「壬辰」「癸巳」が干支になるだろう。何と読むかは、調べてみてほしい。ちなみに、今年2026年の干支は、「丙午」である。始業式でもお話ししたが、なかなか有名な干支の一つである。この干支の年は、子どもが少ない。さて、なぜなのだろうか。これも調べてみてほしい。さらに、先に書いた「甲子きのえね」の年にできた施設がある。毎年春と夏には多くの人が注目するあのボールパークである。さらに、「乙巳」の変、「壬申」の乱、「戊辰」戦争と歴史上には干支を冠した言葉が多い。干支にまつわる話は挙げればきりがないetc.
後藤 秀吉 令和8年1月30日
校長所懐 令和7年12月
サンタクロースとはうまくいったもので、子どもたちにとっては大切な存在である。笑顔を絶やさず、赤い服を着て、赤い帽子をかぶり、黒い靴を履き、白いひげを生やした太りぎみの老齢男性。白い大きな袋を抱え、トナカイのそりで空を飛ぶ。煙突から入って、子どもが眠っている間に、ツリーに飾られた靴下の中にプレゼントを入れる。朝目覚めた時の子どもたちの笑顔に癒される。サンタクロースの起源は、1700年前のミュラ(現在のトルコ)という都市で大主教を務めた聖ニコラウスという人物がモデルになったと言われている。聖ニコラウスが、ある夜お金に困っていた商人の家に行き、煙突から金貨を投げ入れた。するとその金貨は、たまたま暖炉の近くに干してあった靴下に入った。聖ニコラウスが投げ入れた金貨のおかげでその商人の娘たちは身売りをしなくて済んだ。聖ニコラウスはこの他にも数多くの善行を重ね、「罪なき人や子どもの守護聖人」として崇拝されるようになった。聖ニコラウスは英語で「Saint Nicholas(セイント・ニコラス)」。これがなまって「サンタクロース」と呼ばれるようになった。このような経緯で「煙突から家に入り、靴下の中にプレゼントを入れるサンタクロース」というイメージができあがった。彼の思いを受け継ぎ、各地でサンタクロースが誕生していった。
終業式で、全校生徒に向けて「サンタクロースっているんでしょうか?」という130年前のニューヨークのサン新聞の社説について紹介した。生徒たちの心にはどんな思いが浮かんだのだろう。放課後、校長室に2人の生徒が声をかけてきた。「私には(サンタが)来てくれています」と言う生徒と「もう来ませ~ん」という生徒。どちらもに明るくこにこしている。また、職員室にいるときにも「サンタ見えます」「サンタ来ました」と笑顔で伝えてくれる生徒がいた。その時、靴下の中がなんだか温かくなった。今年も子どもたちに素敵なクリスマスプレゼントをいただいた。
後藤 秀吉 令和7年12月25日
校長所懐 令和7年11月
縄とはうまくいったもので、10月に発足した78期生徒会のスローガン「一縄団結~あつまれPtの森」にも縄が使われた。11月26日の朝会で、伊藤百花生徒会長からこんな話があった。「このスローガンには、第78期生徒会が一つの縄(78の読み替え)のように団結して活動するという意味と元素記号78のpt(プラチナ)のように一人一人が輝ける学校にしたいという意味がこめられています。また、ゲーム『あつまれどうぶつの森』が自分たちで島を開拓して良くしていくように、全校で協力して大綱中学校をよりよくしていくという意味もこめられています。」これを聞きながら、一昨年度の卒業式の式辞で縄(正確に言えば、「禍福は糾える縄の如し」という故事成語)について話したことを思い出した。
|
禍福の禍はコロナ禍の禍です。福は幸福の福。つまり不幸や幸福、悪いことや良いこと、つらいことや嬉しいこと、それらは縄のようなものだという意味の言葉です。もう少し丁寧に説明しますと、「糾える縄」とは、撚り合わさってできた縄、縄は数本の紐や藁を編んで作ります。するとある一本が表面に現れると別の一本は裏に隠れてしまいます。人生も良いときが表に現れる時と裏に隠れてしまう時があります。しかし、途中で諦めない限り必ず縄のように良いときが再び巡ってきます。反対に良くないときも同じです。今のあなたは縄のどの面が表に出ているでしょうか。今とても幸福だという人は決して油断したり浮かれたりせず、あなたの周りの人への気配りを忘れずにいてください。今つらい時を迎えているという人は、やがて迎える幸福に向けて、辛抱強くたくましく生きてほしいと思います。「禍福は糾える縄の如し」という言葉をぜひ心にとどめておいてください。そしてもうひとつ付け加えておきます。一人ひとりの縄は、もろく弱いものです。だから一人ひとりの縄を撚り合わせて困難に立ち向かうことが大切です。そういうことを学ぶのが学校という場の大きな意義だと私は思っています。ここは930本の縄が撚り合わされ一本の大きな綱になっていく場所。だからここは大綱中学校というのだと思います。 |
第78期から、縄を連想し、さらには原子番号78のプラチナを導き出す。なかなか洒落ととんちの効いたメンバーがあつまって考え出しただけのことはある。このメンバーで78期はどんな縄を糾い、一本の大きな綱にしてくれるのか楽しみである。
後藤 秀吉 令和7年11月28日
校長所懐 令和7年10月
リハーサルとはうまくいったもので、本番さながらで一度やっておくと改善点も見つかり、心の準備もできてくる。ぶっつけ本番がいいなんて強心臓な人もいるが、そういう人ばかりではない。教師駆け出しのころ、リハーサルは本番と同じように臨まねば意味がないと叱られたことがある。リハーサルだからと気を抜いて、手を抜いて、適当にやった時のことだ。結果、本番もリハーサル通りのひどい合唱になってしまった。今でも苦い経験として残っている。
10月15日は合唱コンクール本番だった。大綱中学校の合唱コンクールは、かけがえのない伝統行事である。それは、3年生の演奏を後輩たちが聞くことが大きな要因になっている。そのためにも一堂に会する場所が不可欠で、近年は、横浜みなとみらいホールや県民ホールを会場としてきた。1、2年生が午前中、3年生は午後の演奏となる。午後の部開始の3年生学年合唱で、食後のたるんだおなかと頭がしゃきっと目覚めるのが恒例となっている。
9月25日、3年生の学年リハーサルが行われると聞き、うきうき気分で体育館へ向かった。整然と移動して歌い始める姿を見て、今年の3年生もいいぞと感じた。ところが、始まってすぐに頭の中に?が浮かんできた。クラスの演奏が進めば進むほど?の数が増えてきた。あと3週間で本番だぞ、大丈夫か。最後に感想を求められたので、正直な思いとして少々苦言を呈してみた。
リハーサルから3週間後。3年生の音のシャワーが、ホールいっぱいに降り注がれた。今年度は日程が昨年度よりも2週間早い。9月12日の夏試験が終わってから本格始動したので、正味1週間でのリハーサルだったのだ。そこからの巻き返しは見事で、今年も3年生が引っ張る大綱中学校ならではの合唱コンクールとなった。練習でもリハーサルでも本番でも、それぞれの「信」が見つかっただろうか。その時できる最善を尽くす。それができたのが今回の合唱コンクールであり、大綱中学校の伝統なのだ。
後藤 秀吉 令和7年10月31日
校長所懐 令和7年9月
長月とはうまくいったもので、30日までしかないのに長い月と名乗っている。日数ではないとしたら、いったい何が長い月なのだろうか。
明日から10月になる。いよいよ衣替えのタイミングである。とはいえ、まだ半袖で十分な気候のため、箪笥の中身を入れ替えるタイミングが難しい。生徒は相変わらずの半袖短パン姿である。秋はとっくに訪れているはずなのに、その体感がない。長期予報では、10月半ばまで最高気温が25℃以上の夏日が続くらしい。朝晩は多少ひんやりするので、寒暖差のためこれまで以上に体調管理が求められる。ここ数日、インフルエンザでお休みする人もちらほら現れている。季節の変わり目は要注意である。
さらに10月の真ん中15日には、合唱コンクールが控えている。今年度から課題曲をなくし、自由曲一曲での闘いとなった。ここからの2週間でどこまで仕上げられるか。各クラス知恵と団結力の見せ所である。あなたのクラスはどんな合唱をめざして日々練習し、どんな合唱を当日披露するのか。そこにどんな「信」を練りこむのか。2週間はそんなに長い時間ではない。だが、あなた次第では長い時間にもなる。自分の可能性を信じ、一所懸命な仲間を信じ、自分たちなりの合唱を発信してほしい。その長い時間の努力は青春といって何よりも尊い。そんな仲間とともに信じ合える体験ができる時間にしてほしい。
あなたにとって長月が濃くて長い月になりますように。
後藤 秀吉 令和7年9月30日
校長所懐 令和7年8月
つながるとはうまくいったもので、漢字は「繫」と書き、「糸」が入っていることから「結びつける」という意味をもつ。スマホの電波がやっとつながったということから、電話や通信が「接続される」といった意味にもなる。さらに、物や電波が結びついたり接続されたりすることから、人との関係や心が通じ合う、理解し合う、触れ合うといった意味にもなってくる。つながりは私たちの身の回りにあふれている。
27日の始業式では、つながりについての話をした。いつもの部屋「つながるーむ」から放送による式だった。大綱中学校にある特別支援教室である。昨年度から校内ハートフル支援員の先生が常勤していて、それまで以上に安心できる場所になった。人と人が、生徒と生徒が、生徒と先生が安心してつながれる場所をみんなでつくっている。2学期始業式が27日ということもあり、「毎月27日は27がる日」にしたいと宣言した。毎月27日には、いつも以上に「つながる」ことを意識してほしいという願いを込めて。
夏休みが終わり、2学期が始まった。暑さは一向に弱まる気がしない。体調管理が難しい時期でもある。夏休みと9月をつなげる一週目が終わり、学校生活のペースは戻ってきただろうか。まだの人は、10日から始まる夏試験に向けて、心とからだの各ピースを一つにつなげよう。
後藤 秀吉 令和7年8月29日
校長所懐 令和7年7月
面談とはうまくいったもので、面と向かって懇談する、つまり顔を合わせてしっかりと話をするということになる。学校では、毎年7月は個人面談(三者面談)を行っている。4月から新しい環境で生活し、40日間の長い夏休みを迎えるにあたって、生徒と保護者と担任とで面談する。私が中学生のころは、この面談は多くの生徒にとって恐怖の時間だった。学校生活の中でも保護者に言い忘れていたこと、中には隠していたことが知られてしまう瞬間だったから。知られて困ることのない人にとっては、そうでもないのだろうが、中学生にもなるといちいち親に言わなくなるので、この面談で暴露される。私の場合は、課題の未提出、テストの悲しい点数、整理されていないロッカー、さらには友人とのトラブルや取り上げられた物などが知られてしまった。親が先生に謝っている姿を見て、絶望を感じた。ところがその後で、担任の先生が「でもね、お母さん…」と私の良いところや頑張っていることを話してくれた。なんだかくすぐったい感覚になった。そのおかげか、家に帰ってからの小言は少なくて済んだ。
私が担任になって面談するようになったときは、このことをいつも心がけていた。課題になることはちゃんと伝える。でも頑張っていることやささいなことでもできたこと、皆のためになったことはもっとしっかりと伝える。中学生の私がされてうれしかったこと、救われたことはとにかくやってみた。どう伝わったか確かめたことはないけれど。
明日からは夏休みに入る。ここまで4か月間、一人ひとりがそれぞれ頑張ってきたのだから、一休みしてみるのもいい。夏休み明けにはリフレッシュした皆さんと対面で談笑できることを楽しみにしている。
後藤 秀吉 令和7年7月18日
校長所懐 令和7年6月
米騒動とはうまくいったもので、今から100年以上も前の大正時代、1918年に起こった約50日間にわたる1道3府37県の計369か所、延べ数百万人が参加した大暴動のことです。記憶に新しいところでは、いまから32年前の1993(平成5)年、記録的な冷夏の影響もあり、米不足となり店頭からお米が消え、米騒動と報道されました。この時はタイ米が話題になりました。日本のお米のおいしさを再確認させられたことを覚えています。その後、日本はどんな政策で、どんな流通で、どんな方法でお米を作り販売してきたのでしょう。今年、3度目の米騒動なるものに直面しました。中学生の皆さんにとっては初めてのことでしょう。今回の米不足の原因については様々な情報が飛び交っています。さあ、あなたどんな答えであなた自身を納得させていますか。単にお米が不作だったから?インバウンドでお米の需要が増えたから?誰かが買い占めているから?万博があったから?政府の政策の影響?それとも…?今、皆さんに求められている力は、情報を集め、正しい判断をする力です。そのうえで正しい行動をとることです。特にネット上にあふれる自由な意見、まことしやかな話など何が本当なのか判断に迷うものが多くあります。初めに米騒動と書きましたが、この表現だって当を得ていると言えないのかもしれません。
おにぎり、おすし、丼などお米は私たちの生活に欠くことのできない主食としてずっと愛されてきました。今、そのお米と真摯に向き合うことで、私たちの社会が抱える種々の課題に気づくチャンスでもあります。さあ、考えてみましょう、あなたなりのコメントを。え、米不足だから「ノーコメント」?!
後藤 秀吉 令和7年6月28日
校長所懐 令和7年5月
日和とはうまくいったもので、ここ数日は空模様を気にする日々が続いた。今日は、予報通りの雨。時に雨脚が強まることもあり、昨日がいかに恵まれていたかを改めて実感させられた。昨日の最高気温は21℃、太陽も雲の合間から差し込む程度で、スポーツをするにはうってつけのコンディションだった。
開会式が時間通りに始まった。先頭で校旗を掲げる生徒会長、その後ろにスポーツ旗を掲げるは3色の応援副団長と体育祭実行委員長。晴れがましい姿だった。青組団長からの優勝旗返還、生徒会長の言葉、二人の実行委員による競技上の注意と式はスムーズに流れ、3人の応援団長による迫力満点の選手宣誓が行われた。準備体操、切り絵イラスト部と美術部による装飾や看板の紹介が終わるといよいよ競技の開始だ。100m徒競走。最後まで真剣に走る姿とそれを力いっぱい応援する姿に体育祭という行事がもつパワーに衝撃を受けた。次のO—1(オーワン)グランプリで、ハードル、縄跳び、ぐるぐるバット、麻袋と悪戦苦闘しつつもあきらめない姿を見て確信を得た。今年の体育祭も大綱中の良き伝統を引き継いだ素敵な体育祭になると。各色の応援発表もまさに甲乙つけがたいまとまりのあるものだった。時間が押して3年生の学年種目は昼食後になったが、最後の色別対抗リレーでは会場全体が一つになって盛り上がった。今年も大綱中らしい一所懸命に頑張り、一所懸命に応援する体育祭になった。
5月になってからは、初夏の暑さと春の温かさや肌寒さがランダムに訪れた。さらには4月からの緊張が緩み、心も体も管理が難しかった。そんな時期だからこそ体育祭のもつポテンシャルの貢献度は高い。がんばった自分への自信やがんばった仲間への信頼が生まれていた。5月29日は天候も取組もまさに体育祭日和だった。
後藤 秀吉 令和7年5月30日
校長所懐 令和7年4月
令和7年度が始まりました。大綱中学校に赴任して4年目となります。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
信とはうまくいったもので、「信」という文字は、「まこと、偽りがない、信じる、しるし、任せる、手紙、便り」といった意味をもち、「信実」「信用」「信頼」「信念」「信任」「確信」「過信」「自信」「所信」「不信」「信条」「信心」「信託」「交信」「通信」「送信」「受信」「返信」「発信」「音信」といった言葉に使われます。
入学式で新入生への式辞の中でも、「信」について次のように触れました。
皆さんに今日伝えたい言葉は、「信は力なり」という言葉です。信は信じるの信です。信じることでパワーが生まれる。これは、京都にあった伏見工業高校ラグビー部で受け継がれてきた言葉です。仲間を信じられるか。頑張った自分を信じられるか。信じられるだけの努力をしてきたか。すべて信じられたときにとてつもない力が発揮されます。皆さんは、まずは「自分を信じる」ことから始めましょう。中学生になると、小学生のときとは違うことに日々直面します。できないこと、わからないことにも直面します。その時、あなたはどうしますか。努力して克服できれば何よりいいことですが、うまくいかなかったときはどうしますか。誰かのせいにして放っておきますか。そうするとどんな中学校生活が想像されますか。大切なことは、結果だけではないということです。自分自身をふりかえり、そして努力した自分がいたらそれは認めていく。自分を信じるとはそういう意味です。まずは、そこから始めてみましょう。
大綱中学校の生徒の皆さん、信じられる自分(の努力)を見つけられる1年間をぜひ体験してください。そして、そんな仲間に気づいたら、心から素直に応援してください。そういう学校を皆で作り上げていく年になると私は信じています。
後藤 秀吉 令和7年4月7日