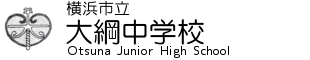令和6年度 校長所懐
校長所懐 令和7年3月
春は別れの季節とはうまくいったもので、3月25日は令和6年度の修了式だった。3年生のいなくなった体育館は、思った以上に喪失感があった。1、2年生には「自分で考え、判断して、行動する」ことがどれだけできたかを今年度のふりかえりとして話した。さらに、4月から始まる新年度に向けて、新しい自分に変わろうとしている人には良いタイミングであること、そして変わろうとしている仲間がいたら応援してほしいということも話した。修了式に引き続き、退任式が行われた。体育館の後ろにはいつの間にか、卒業したばかりの3年生が座っていた。別れの季節。真剣に話を聞いている生徒の姿を見ていると、私の脳裏に懐かしいメロディが奏でられてきた。8分の6拍子のあの曲だ。令和の今ではもう聞くことはほとんどない。スコットランド民謡がもとになっているともいわれるその曲の最後は『Ah,it's a time for fond regrets, When school-mates say "Good Bye."』(訳: ああ、これぞ惜別の時、級友たちの言葉は「さよなら」)ピンとこない人には、「今こそ別れめ いざさらば」と言えばわかるかもしれない。言わずと知れた「仰げば尊し」である。じつにきれいな旋律で、聞いていると心が洗われる。この曲を歌っていた生徒の姿、涙がよみがえってくる。ステージで話している先生とそれを聞く生徒が私の頭の中で過去の映像に溶け込んでいく。暫しタイムスリップ。これぞ教師の特権なんだろうと思う。
4月7日には新たな出会い、8日には再び別れのときがやってくる。出会いは瞬間、別れは突然。この繰り返しである。令和6年度の大綱中学校よ、ありがとう、いざさらば。
後藤 秀吉 令和7年3月27日
校長所懐 令和7年2月
2月最終週になり、日中はマフラー、手袋、コートがいらない陽気に春の忍び足が聞こえてくるようだ。週末は20℃近くになるとの予報もあるので、そろそろ春物へ衣替えを始めようかと思う。
さて、2月は日数の少なさ以上に短く感じる月である。1週目に児童生徒交流日の部活動体験、2週目には冬試験と公立高校共通選抜(いわゆる高校入試)があり、3週目はテスト返却と3年生の卒業期特別カリキュラム開始、4週目は振替休日で始まり4日間で終了。やはり物理的にも心理的にも短い。日没時間は長くなり、下校時刻も遅くなったのに。
冬休み明けの1月も駆け足で過ぎたが、2月は加速する。そして3月はさらに体感速度が増す。毎年のことではあるが、3月に向けて学校はそわそわしてくる。年度末。卒業。今年の卒業生は一緒に大綱中学校に来て、ともに3年間を歩んできた。入学式で話したこと(愛)にいち早く反応してくれた人たちである。あと12日で卒業証書授与式。どんな表情で卒業証書を受け取ってくれるのか楽しみである。3年生だけでなく、1、2年生も3月はそれぞれの学年の締めくくりの時になる。4月からやってくる新入生をリードできる先輩になれるか。大綱中学校の卒業生たちのように、あこがれる存在になってくれることを願う。
今日も温かい日差しが降り注ぐ日となった。それに呼応するかのように鼻とのどがむずむずとしてくる。目も心なしか痒みを感じる。春とともに杉の木からも忍び足が聞こえてくる。はっくしょん!
後藤 秀吉 令和7年2月28日
校長所懐 令和7年1月
節分とはうまくいったもので、毎年2月3日は豆まきをしている。近年は、恵方巻を食べることも広まっている。日本各地でそれぞれの風習があるそうだが、今後どんな風習が広まってくるか楽しみである。さて、冒頭に「2月3日は」と書いたが、カレンダーを見て驚いた。節分の文字が2月2日に書いてある。節分は2月3日に決まっていると思い込んでいたので驚いた。
そもそも節分という漢字から考えてみた。節を分けると書く。節とは季節のこと。四季というように、春夏秋冬である。節分は季節の分け目になる日のことを言うので、つまり年4回ある。季節の始まりは、立春、立夏、立秋、立冬という名で知られている。つまりその前日が「節分」ということになる。2024年は、立春は2月4日、立夏は5月5日、立秋は8月7日、立冬は11月7日だったのでそれぞれその前日が節分だった。2025年も立春が2月3日となる以外は同じである。子どもの頃からずっと節分の豆まきは2月3日にしていた記憶しかなかったので、初体験…と思いきや、4年前の2021年も2月2日だったそうだ。今後は2057年までは4年に1回、節分は2月2日になるそうだ。固定観念とは怖いものだと思い知らされた。
今年の節分をきっかけに、固定観念(思い込みや先入観)を見つめ直そうと思う。1日の生活の中に、実に多くの固定観念があることに驚かされた。改めるべきことや切り捨てること、独りよがりにならず人の言うことを聞くことで節分ならぬ「切聞」を迎えたい。
後藤 秀吉 令和7年1月30日
校長所懐 令和6年12月
キャリアとはうまくいったもので、学校では専らキャリア教育という名で浸透している。これは、平成23年1月31日の中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方 について」に基づいて行われている。そこには「人は、他者や社会との関わりの中で、職業人、家庭人、地域社会の一員等、様々な役割を担いながら生きている。」と始まり、「人は、このような自分の役割を果たして活動すること、つまり「働くこと」を通して、人や社会に関わることになり、その関わり方の違いが「自分らしい生き方」となっていくものである。このように、人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ねが、「キャリア」の意味するところである。」と続いている。「働くことの意義」をしっかりと見つめなさいということだが、背景には当時増えていたフリーターの存在もあるそうだ。人はなぜ働くのか。働かねばならないのか。キャリア教育を通して子どもたちに考えてもらおうということだろう。それから十数年経ち、今やどこも人手不足は否めない。キャリア教育の成果が問われる。
12月13日には、2年生がキャリア学習で「職業講話」を体験した。経済同友会から10名の経営者に来ていただいた。今回は、アイダ設計、アイロボットジャパン、アシアル、開倫塾、東和エンジニアリング、日本情報通信、東日本銀行、ワイ・ディ・シー、BTジャパン、ETSホールディングス(五十音順)から「代表取締役社長・代表執行役員社長・取締役・専務取締役」の方々である。まずはその肩書に驚かされた。講話の内容もたいへん豊かで、会社の概要や仕事の内容、さらには自らの趣味や体験談、特にうまくいかなかったことや人生の転機など、中学2年生にわかりやすく講演してくれていた。子どもたちのキャリア形成に影響を与えてくれる貴重な時間となった。
さて、今年もあとわずか。キャリアの語源はラテン語の「carraria」(荷車の通り道)。転じて、人生の道筋や足跡、そこから仕事における経験や成長、個人の生き方そのものを指す言葉になった。2024年、あなたのキャリアはどうだっただろうか。自分が引いた荷車の跡をふりかえってみたい。
後藤 秀吉 令和6年12月25日
校長所懐 令和6年11月
語呂合わせとはうまくいったもので、11月は他の月と比べて語呂合わせが盛んな月のようである。というのも11が「いい」と読めるため、11月○日を「いい○○」と呼べるからだろう。ざっと調べても約200種類もあり、その中で「いい○○の日」というのは、17日、36種類もある。いい日はいくつあってもうれしいからなのだろう。今日29日は、「いい肉の日」としてよく知られている。しかし、どうしてと首をかしげてしまう日もある。いい夫婦の日は1122でわかりやすい。いい文の日も1123と想像がつく。いい風呂の日は1126、いい石1114、いい色1116などもそのままである。いいお尻の日というのもあるが、さて何日だろう。極めつきは「いい乾物の日」。超難問である。やはり、わかりやすく親しみのある語呂合わせがいい。
11月を振り返ってみると、1日に学校運営協議会が開催された。大綱中学校のことを真剣かつ親身になって考える委員が集まり、毎回熱く議論している。6日には2年生が総合的な学習でキャリア教育(ライフデザイン)を行った。11日からは3年生の秋試験が始まり、12日からは全学年が秋試験になった。そのころから、気候も秋らしくなり、日没もつるべ落としのごとく早くなった。最近は17時にはかなり暗く感じるようになった。次に登校するときはもう12月になっている。令和6年もあと1か月。どんな締めくくりを迎えるのだろう。
今日11月29日は、いい肉以外にも「いい服の日」でもあるらしい。寒くなってきたので、いい(防寒)服でも買ってみようかと思う。ちょうど11月29日はブラックフライデー。
後藤 秀吉 令和6年11月29日
校長所懐 令和6年10月
コンクールとはうまくいったもので、「特定のテーマを指定して参加者を募り、作品のできばえや技能・演技などの優劣を競う催し」という意味で使うことが多い。世の中にはたくさんのコンクールがある。日本音楽コンクール、ピアノコンクール、吹奏楽コンクール、バレエコンクールなどが一般的だが、中にはワインコンクールやチーズコンクールなどといった洒落たものもある。コンクールがフランス語から生まれた言葉ということから納得してしまう。英語では、コンテストやコンペティションが同類の言葉である。
大綱中学校では、毎年10月は合唱コンクールの時期である。昨年に引き続き「横浜みなとみらいホール」で開催した。やはり素晴らしいホールで、すべての合唱が格段に美しく聞こえる。まるでシャワーのように天井から歌声が降り注いでくるかのようで、しばしうっとりとしてしまう。1年生は初めての合唱コンクールで朝一番の発表ではあったが、8クラスすべてが堂々と歌った。最高の滑り出しであった。続く2年生もさすが先輩といった雰囲気で、ワンランク上の発表を披露した。午後になり、満を持しての3年生の発表。最初の学年合唱で後輩たちは度肝を抜かれたはずだ。天井から降ってくる音のシャワーの量と質が、午前中のそれとは全く違っていた。心地よい鳥肌が立った。大綱中の伝統はしっかりと引き継がれていると確信した。当然のことながら、3年生の発表はすべて感動的だった。コンクールなので賞が決められる。金賞・銀賞・銅賞と8クラス中3クラスのみ表彰される。これも世の習い。「みんな良かったよ」でもよいのだが、コンクールと名の付く以上順位は決める。そしてそこには必ず理由がある。そしてそこには必ず続きがある。大切なのはいつもその後なのだ。
合唱コンクールはドラマチックである。困って、苦しんで、仲間とともに乗り越えて、そこから得るものがとても大きい。合唱困苦得る。
後藤 秀吉 令和6年10月31日
校長所懐 令和6年9月
お月見とはうまくいったもので、眩いばかりに輝く満月を見ていると胸の奥がぞくぞくする妖しい気持ちになってくることさえある。一方で細くゆったり浮かぶ三日月を見ていると風に揺れるベッドに横たわるような睡魔に襲われる。月はどの形でもいつも魅力であふれている。
テレビで流れてくるCMで、この1か月でよく耳にしたのが「月見○○」なる商品だ。ファーストフードはバーガー類や丼などにその名を冠している。中には普段と同じものなのに、目玉焼きを乗せたものを月見ハンバーグと名前を変えて売ったらいつも以上に注文されるようになったという実証実験のような報道もあった。これも月見という言葉のもつ力なのか。
さて、暑かった9月もここのところ涼しいという形容がはまりつつある気候になった。秋がするりと滑り込んできたかのようである。虫の音も耳に心地よい音にバトンタッチされた。そろそろ秋の味覚も出回るのだろうか。半袖を箪笥へとしまい、待ち焦がれた秋を堪能したい。今週は生徒会本部役員選挙の活動が始まり、毎朝校門では立候補者と応援者の挨拶でにぎわっている。これも秋の風物詩の一つである。この熱戦は、10月4日の立会演説会・投票まで続く。
夜空を見上げると、月がずいぶんと痩せてきた。あと5日もしたら新月。その翌日には新生徒会本部役員が誕生している。新月とともに新大綱中学校生徒会が始まる。月が日に日に大きくなるように、新生徒会も大きく輝いていってほしい。
後藤 秀吉 令和6年9月28日
校長所懐 令和6年8月
台風10号とはうまくいったもので、毎年1月1日から生まれる台風には番号が振られている。10号だから今年10番目に生まれた台風ということになる。台風10号はずいぶんとゆっくりと進むタイプで、ジョギング並みというから厄介である。ニュース等で被害が映し出されるたびに心が落ち着かなくなる。
学校では、登下校や外での活動に影響が出た。始業式の火曜日は防災訓練を延期にした。ゆっくり進むため、今日金曜日までに直撃は免れたが、心配が来週まで持ち越されることになった。土日に試合等が組まれている競技は、天気予報とにらめっこになっているだろう。夏休みが明け、2学期が始まり、さあがんばるぞという思いに水を差されたといった状況である。
ところで、台風10号には、名前がついているのをご存知だろうか。「サンサン」という。漢字もあり、珊珊と書く。激しい風雨に似合わずかわいらしい名前である。香港の少女の名前らしい。9号は「ジョンダリ」で8号は「ウーコン」。つまりすべての台風に名前がある。しかも、なんと11号の名前はすでに決まっている。「ヤギ」。そう動物のヤギである。なんと台風には140個の名前が用意されているそうだ。その中の10個が日本語の名前になっている。「ヤギ」のほかに、「コイヌ」「ウサギ」「カジキ」「クジラ」「トカゲ」「ヤマネコ」「コグマ」と動物ばかりと思いきや「トケイ」や「コト」もある。これら10個には共通点がある。わかるだろうか。台風の時には見えないが、台風が過ぎた後の夜空には見えるかもしれない。
次に登校するのは9月。台風10号「サンサン」は通過していることを願う。すると厳しい残暑が復活する。台風もつらいが猛暑もつらい。そして11日からは夏試験が始まる。夏休みに緩んだ心と体には耐えがたい日々になっている。耐風重剛。ちょっと重すぎたかも。
後藤 秀吉 令和6年8月30日
校長所懐 令和6年7月
警戒アラートとはうまくいったもので、ここ数日の暑さは気合いとか我慢とか根性とかでは乗り切れるレベルをはるかに超えている。だから熱中症警戒アラートや特別警戒アラートなるものまで発して、呼びかけているのだろう。それはとても大切なことであり、アラートがなくとも、一人一人が自らの体調を管理できるようにならないといけない。
ところで、ずっと気になっていたのだが、「警戒アラート」という表現がどうも耳障りがよくない。「アラート」が警告、警報、警戒といった意味の言葉なので、「警戒アラート」は「警戒警戒」となる。これってよくある重複表現ではないか。例えば、「頭痛が痛い」「一番最初」「事前予約」「伝言を伝える」「あとで後悔する」「過半数を超える」「満天の星空」「後ろから羽交い絞め」など、普段我々がうっかりと使ってしまう表現である。カタカナや英語が混じるとなんだかわからなくなる。最近、ニュースで流れてくるカタカナ用語に少々辟易しているということも耳障りの原因になっているのかもしれない。さらに、若者の使う流行語や略語にもついていけていないことも影響しているのかもしれない。いずれにしても、今年の暑さは、「警戒警戒」しなくてはいけないくらい危険なものであるということは間違いない。熱中症は暑さだけが原因ではなく、日々の生活も影響すると聞いている。食事での栄養補給、十分な睡眠と休養がないと、思わぬところで足をすくわれかねない。
夏休みはあと1か月。長期の休みだからこそ体験できることにチャレンジしてほしい。特に自分が暮らす地域のお祭りにも足を運んで、体を動かしてほしい。今、校庭の片隅には明日の出番を待つ櫓が鎮座している。明日も警戒アラートは発令されるだろうが、櫓の上のバチさばきは、いつ見ても軽快である。
後藤 秀吉 令和6年7月26日
校長所懐 令和6年6月
総会とはうまくいったもので、学校では毎年この時期に生徒会が中心になって、本部や各委員会の年間計画や予算について全校生徒で議論するいわゆる生徒総会が行われる。全校生徒が一堂に会して行えればよいのだが、スペースの関係、感染症対策、暑さ対策など様々な観点から考えて、今年度も放送による開催となった。生徒は自分の教室で参加し、生徒会本部役員や委員長たちは別会場の図書館からリモートで提案した。Chromebookの接続確認や定足数確認が済み、生徒会副会長の開会宣言で幕を開けた。生徒会長のあいさつの後、第1号議案の提案と審議、第2号議案の…と続いた。第4号議案で、雨天時以外でのトランプ等の貸し出し【生活委員】 第5号議案で、委員長選挙の廃止【選挙管理委員会】 第6号議案で、選挙時の推薦母体の撤廃【選挙管理委員会】の3つが採決となった。事前に周知されていたことなのですんなり可決となると思っていた。ところが、第5号議案は否決となった。これは、深く考えずに賛成というわけではなく、しっかりと意見を聞き、『自分で考えて行動しよう』という私が始業式で話したことに通じる、自分で考え行動した結果が現れた瞬間だった。
梅雨になり、安定しない天候が続き、気持ちも体も不調になるこの頃ですが、今回の生徒総会は久々に、爽快だった。
後藤 秀吉 令和6年6月28日
校長所懐 令和6年5月
健康診断とはうまくいったもので、学校では毎年この時期に内科、歯科、眼科、耳鼻科の検診、心電図検査や尿検査そして身長、体重、視力、聴力と枚挙にいとまがない。これを法律(学校保健安全法と同施行規則)では、6月30日までに実施することと定められています。授業中に呼ばれて検査に行った記憶がある人もいることでしょう。授業がつぶれて喜ぶなんて生徒もいますが、教師の立場では、授業の途中で検査に行くので、計画がくるってしまいます。同じクラスばかりが検査に当たってしまうと、テスト前にあたふたすることになります。しかしながら健康診断は、それこそ命にかかわる大切なことなので何とかやりくりします。
大綱中の生徒たちは、いつも整然と検査に臨んでいます。これは素晴らしい伝統の一つです。校医さんたちにもほめていただいています。心電図検査は1年生だけでしたが、小学校1年生の時以来なので、緊張や不安があったのかやや落ち着かない人もいたそうです。すべての検査が終わるのが、6月20日の予定です。途中には春試験もありますので、1回1回の授業をより集中しないといけません。
今週末は体育祭です。天候が心配されますが、まずは体調管理です。季節の変わり目で、疲れが出やすい時期です。やはり食事と睡眠、規則正しい生活です。天候は心配してもどうなるものでもないのですが、気になって何度も天気予報を見たり、空模様を見たりして、天候診断しています。
後藤 秀吉 令和6年5月27日
校長所懐 令和6年4月
令和6年度が始まりました。大綱中学校に赴任して3年目となります。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
花見とはうまくいったもので、入学式の前日に家族で近くの公園へ出かけてみました。行楽日和とあって、樹の下は花吹雪を楽しむ家族連れやカップルで賑わいを見せていました。ここでふと気づいたことですが、花は百花繚乱というように何種類もあるのに、花見、花吹雪といえば「桜」の花を指します。花屋で花束を買うときにはたくさんの花なのに。なんとも不思議です。
令和6年度は、938名の生徒とともに大綱中学校の第78期が始まりました。子どもたちには、それぞれの個性を大切に、それぞれの色や形の花をそれぞれのタイミングで咲かせてほしいと願っています。そのために教職員、保護者、地域の大人が手を取り合って支援していきたいと考えています。入学式では、今年度も「愛」についての話をしました。始業式では、まず自分で考えてから行動することについて話をしました。大綱中学校の生徒たちは、しっかりとした目で話を聞いてくれました。
桜の花がこんなにも咲いている4月の始まりは久しぶりです。今週末もまだ花見ができるかもしれません。9日の嵐でずいぶん散ってしましましたが、10日には違う嵐が話題になりました。♪サクラ咲ケ きみの胸の中で♪
後藤 秀吉 令和6年4月11日