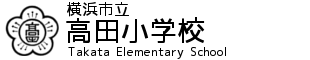【4年生】理科「雨水のゆくえと 地面のようす」実験「水のしみこみ方」(9月)



9月11日、関東地方に大雨が降り、校庭が海のように雨水でいっぱいになりました。ですが、翌日の朝、水がなくなりました。このようすから、子どもたちは「あんなにあった雨水は、どこにいったのだろう。」と疑問をもち、「排水溝に流れた」「土にしみこんだ」という予想をし、確かめることになりました。
今回は、「土にしみこむ」という考えから、しみ込み方に「土やすなのつぶの大きさ」が関係があることを予想し、実験をしました。
結果から、水のしみこみ方には、つぶの大きさが関係していて、土やすなのつぶが大きい方が水がしみこみやすいということがわかりました。
この大雨の出来事から、お風呂や洗面台等で水が流れるよう斜めになっていることや、駐車場に砂利がしいてあるのは水をしみこみやすくするためだと、学習とつなげて、理由を考えました。子どもたちが、身近な生活に学習が関連していることを発見したときは、うれしそうでした。
登録日: / 更新日: