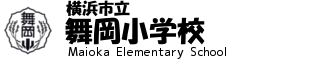“安心”・“居場所”(令和7年8・9月号)
“安心”・“居場所”
校 長 田中 秋人
朝夕の風にほんの少し秋の気配を感じるようになってきました。かつては、午後になると入道雲が出て、きっと夕方には雨が降り、夕立になるなぁと、空を見上げながら季節の移ろいを感じていたものです。しかし、最近では「線状降水帯」という言葉がニュースによく登場するようになり、自然の表情も、私たちの受け止め方もずいぶん変わってきたように思います。この度の豪雨災害で親戚の方やご友人が被害に遭われた方もいるかと存じ上げます。謹んでお見舞い申し上げます。
さて、長い夏休みを終え、子どもたちが元気に登校してくる姿に、学校にも再び活気が戻ってきました。久しぶりの教室で、友だちとの再会に笑顔を見せる子どもたちの様子は、何よりも嬉しい光景です。夏季休業のはじめの数週間は校内研修や美化作業などに追われ、慌ただしく過ぎていきました。子どもたちがいない校舎で、先生方と一緒に環境を整えながら、夏休み明けの準備を進めたり、よりよい授業を行うためにはどうすればよいか研修を行ったりする日々でした。そんな時期が過ぎ閉庁期間に入ると、少しだけ時間に余裕ができ以前から気になっていた本屋大賞を受賞した作品の映画を観ることができました。その物語は、学校に行けなくなった女の子が、ある不思議な場所で、同じように心に傷を抱えた子どもたちと出会うというものです。その場所では、誰もが最初は距離を取りながらも、少しずつ互いの存在を認め合い、心を通わせていきます。ある男の子は、明るく振る舞いながらも、家庭の事情で心に深い孤独を抱えていました。誰にも弱音を吐けず、笑顔の裏で必死に自分を保っていた彼が、ある日「誰かに気づいてほしかった」とつぶやいたとき、場の空気が変わりました。誰も彼を責めず、ただ静かに受け止める仲間たちの姿に、胸が熱くなりました。また、別の女の子は、学校での友人関係が原因で心を閉ざしていました。人と関わることを避けていた彼女が、仲間の優しい言葉に少しずつ心を開き、ある場面で「ここにいてもいいのかな」とつぶやいたとき、その言葉にうなずく仲間たちのまなざしが、彼女の居場所をそっと照らしていました。
それぞれが違う悩みを抱えながらも、誰かに受け止められることで、少しずつ自分を取り戻していく姿に、「人は、理解されることで前を向けるようになる」ということを改めて感じました。
私たちの学校にも、さまざまな思いを胸に登校してくる子どもたちがいます。元気いっぱいに見える子も、静かに過ごしている子も、どの子もそれぞれの背景や気持ちを抱えて、日々を過ごしています。だからこそ、私たち大人は、子どもたちの小さな変化やつぶやきに気づける存在でありたいと思います。「大丈夫?」と声をかけること、「よく頑張ってるね」と認めること、「そばにいるよ」と伝えること。そんなささやかな関わりが、子どもたちにとっての“安心”や“居場所”につながっていくのだと思います。
7月末に行われた町内会のお祭りでの休憩時間に行われた舞ソーランにはたくさんの在校生や卒業生が参加していました。これも子どもにとっての一つの居場所だと思います。子どもたちにとって “安心”や“居場所”が作られるように子ども面談などで声を聞きながら、今後も学校教育活動を推進していきます。どうぞよろしくお願いします。