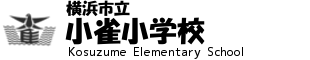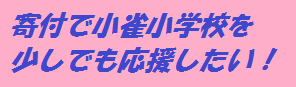令和7年度 学校だより 3月号
|
令和7年度 3月号
|
|
夢八訓 ~夢をもち続ける~
|
|
|
|
3月19日に第57回卒業証書授与式が行われます。今年度の卒業生は80名で、本校では一番人数の多い学年です。この一年間最高学年として活躍し一段と成長しました。保護者、地域の皆様には、6年間という長きにわたり子ども達を見守り支えていただきましたことに深く感謝申し上げます。
卒業生には、小学校6年間の思い出を胸に、これからの中学校生活を楽しく、そして豊かに過ごしてくれることを願っています。そして、この先続く人生において、「夢をもち続ける」ことを大切にしてほしいと思います。「夢八訓~夢をもち続ける~」という題で、卒業文集に寄稿しました。
夢の大切さを表すものとして「夢八訓」という「夢」から始まる、八つのステップを表した言葉があります。流通評論家、故吉田貞雄さんが書いた「夢」という詩の冒頭フレーズです。
「夢」のある者には「希望」がある 「希望」のある者には「目標」がある
「目標」のある者には「計画」がある 「計画」のある者には「行動」がある
「行動」がある者には「実績」がある 「実績」のある者には「反省」がある
「反省」がある者には「進歩」がある 「進歩」がある者には「夢」がある
「夢」→「希望」→「目標」→「計画」→「行動」→「実績」→「反省」→「進歩」→「夢」
「夢」から始まり、また「夢」に戻ってきます。この八つのプロセスを一歩ずつ進んでいくことによって、自分の成長や成功につながったり、夢の実現に近づいていけたりするということを感じさせてくれる言葉です。
いきなり、『夢をもて』『夢を語れ』と言われても、まだ漠然としていて分からないという子も多いかもしれません。「夢」というのは、『どういう仕事に就きたいか』という将来の職業だけを指しているのではありません。『どういう人になりたいのか』『どういう人生を送りたいか』というのも「夢」のひとつです。
今はまだはっきりとした「夢」がない場合は「目標」から始めてみるのも手です。小さな目標でも大きな目標でも、近い目標でも、少し先の目標でも、目標であれば決めることができます。「目標」からスタートさせた「夢八訓」のサイクルの中でも、「夢」を見付けることができます。「計画」のある者には、「行動」があり、「実績」があるのですが、この「実績」の中には、【失敗】も含まれます。行動の結果、うまくいくことばかりではありません。しかし「実績」【失敗】の中から生まれる「反省」をすることが大切です。自分を振り返る「反省」あるところに「進歩」があり、その先の「夢」につながります。
夢を力に、卒業生一人ひとりが自分の夢を見付け、そして、その夢の実現に向けて一歩一歩しっかりと歩みを進めていくことを願っています。
本校では、子ども達の夢や希望を育みながら、まちと共に歩む学校づくりを推進しています。学校・家庭・地域の中で自己有用感や多くの達成感を感じ、なりたい自分に向かって努力し続ける意欲を高められるよう、保護者や地域の皆様とも手を取り合い、これからも力を尽くしてまいります。
3月号の詳細は、すぐーるで配信しております。
|
登録日: / 更新日: