

2月17日、避難訓練がありました。今回は、避難訓練があることは予告していますが、地震なのか火災なのか、または両方なのかは、放送の指示を聞かないと避難経路がわからないという設定でした。訓練を重ねてきて、比較的授業時間中は指示を確認したり、「おかしもち」の約束を守って避難しています。休み時間や掃除の時間、給食の準備や片付け中など、自分たちで身を守る行動ができるように、今後も取り組んでいきます。




2月16日、今年度最後のクラブ活動がありました。6年生にとっては、小学校生活最後のクラブ活動です。活動の振り返りをするとともに、最後の活動を楽しむ姿がたくさん見られました。




よつば組が、19日の合同学習発表会に向けて、リハーサルを行いました。校内での発表も兼ねていて、たくさんのクラスが発表を見に行きました。発表のあとには、鑑賞した人の中から感想の発表がありました。堂々と発表する姿に、よさを伝える声や応援の声が聞かれました。




2月13日、たてわり活動がありました。この日は、1~5年生までがたてわり教室に集まり、20日に行う予定の「6年生を送る会」の準備をしました。メッセージカードや各学年からのプレゼントを確認したり会の進行を確認したりしました。5年生は初めて6年生のいない状態でたてわり活動をリードする取組を行い、最高学年に向かう気持ちを高めているようでした。
6年生は、別室で下級生へのメッセージづくりをしました。お互いの相手を思う気持ちが伝わってきて心が温かくなりました。






2年生が、生活科で冬野菜の栽培に挑戦しています。観察を続け、夏野菜との違いにも目を向ける学習です。学年で育てている大根は収穫して大根試食会を行う予定です。




6年生の図工で取り組んだ絵が廊下に展示されています。宮沢賢治さんの作品を読んで、言葉からイメージしたこと感じとったことを、形や色、画面構成、表現方法を工夫して表しています。一つ一つの作品に工夫が感じられて、思わず見入ってしまいます。




2年生が、図工でカッターナイフを使った学習をしていました。色画用紙で作った建物にカッターで窓を開け、その中に絵柄を表現します。刃の出し方や刃を当てる角度、紙の押さえ方など、手指の安全に注意して行いました。子どもたちは、窓を開けるときのワクワク感を想像している様子で、集中して取り組んでいました。




2月の1週目、各クラスの「あいさつ隊」の人が、朝、門のところに立ち、あいさつ運動を行いました。さわやかな朝に「おはようございます」という元気な声が響きました。明るい声で挨拶を交わすことは、相手への思いやりを育てるだけでなく、自分自身の気持ちを前向きにし、学校全体に温かい雰囲気を生み出します。

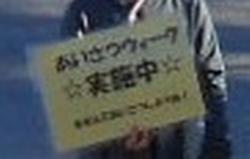


6年生が体育で、ティー・ベースボールに取り組んでいました。打ったボールをキャッチする際にグローブの感触を体験しようと、大谷選手からいただいたグローブを使いました。実際に使ってみた人は、打球を積極的に追いかけ、グローブの感触を確かめていました。




3年生が理科で、豆電球を使った実験をしていました。明かりがつくつなぎ方を確かめたあとは、その回路を使って電気を通すものと通さないものを調べていました。子どもたちは、これまでの生活経験から予想を立てて取り組んでいました。



