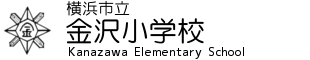沿革
学校のあゆみ
|
明治6(1873)年 |
・洲崎の龍華寺に「知足学舎」できる。(今の金沢小学校の始まり) |
| 明治8(1875)年 | ・柴村の小学舎を、知足学舎と合わせる。 |
| 明治25(1892)年 | ・野島学校を知足学舎と合わせる。 |
| 明治26(1893)年 | ・校名を「尋常高等金沢小学校」とする。 |
| 明治41(1908)年 | ・児童の数がふえたため、授業を1日2回に分けて行う。 |
| 明治42(1909)年 | ・洲崎の民家を借りて分教場をつくる。 |
| 明治44(1911)年 | ・町屋に新しい校舎ができる。昔の校章ができる。 |
| 大正元(1912)年 | ・昔の校歌ができる。 |
| 大正12(1923)年 |
・校名を「金沢尋常高等小学校」とする。 ・関東大震災がおきて校舎がくずれる。このため、町屋神社・称名寺・宝蔵院の境内で、屋外での「林間教授」が行われる。 |
| 大正13(1924)年 |
・バラック校舎をつくり、授業を2回に分けて行う。 ・新しい校舎ができる。 |
| 昭和11(1936)年 |
・飛行機の格納庫だった建物をつくりかえて、「唱歌室」をつくる。 ・校名を「横浜市立金沢尋常高等小学校」とする。 |
| 昭和16(1941)年 |
・太平洋戦争始まる。 ・校名を「横浜市立金沢国民学校」とする。 |
| 昭和19(1944)年 | ・戦争がはげしくなり、初等科3年生以上の525名は、中郡東秦野村に集団疎開をする。 |
| 昭和20(1945)年 |
・さらに戦争がはげしくなり、入学式の後、すぐに学校へいさをする。 ・北側にあった校舎の8つの教室を、「鹿島航空隊」隊員の宿舎として使う。 ・集団疎開の児童が1年3か月ぶりにもどってくる。 |
| 昭和22(1947)年 | ・校名を「横浜市立金沢小学校」とする。 |
| 昭和24(1949)年 |
・全校舎に水道がひかれる。 ・児童図書館ができる。 |
| 昭和26(1951)年 |
・児童の数が3,435名にふえる。校舎を新しく建ててふやしたが追いつかず、1日2回に分けて授業を行う。 ・八景小学校、文庫小学校がそれぞれ独立する。 |
| 昭和27(1952)年 | ・八景小・文庫小の工事が終わり、職員・児童の引っこしがすべて終わる。 ・全学年にわたって、1日2回に分けて授業をせずにすむようになる。 ・完全給食を始める。 |
| 昭和28(1953)年 |
・暖房設備が完成する。 ・創立80周年を記念する式典が行われる。 ・今の校歌ができる。 |
| 昭和32(1957)年 | ・「ひなまつり学芸会」に、アメリカンスクールの児童40名が来校する。 |
| 昭和43(1968)年 | ・プールが完成し、プール開きが行われる。 |
| 昭和45(1970)年 | ・今の第2校舎(3階建て11教室)が完成する。 |
| 昭和49(1974)年 |
・創立100周年を記念する式典が行われる。 ・第1校舎の西半分が新しくなり、今の第3校舎ができる。 |
| 昭和52(1977)年 |
・特別教室(理科室・音楽室)と、普通教室3教室ができる。 ・戦前からただ一つ残された木造校舎がとりこわされる。 |
| 昭和57(1982)年 | ・第1回の「全校砂遊び大会」が行われる。 |
| 昭和58(1983)年 |
・第1回の「全校たこあげ大会」が行われる。 ・箱根夏季学校が始まる。 |
| 昭和59(1984)年 |
・家庭科室・玄関ができる。 ・創立110周年を記念する式典が行われる。 |
| 昭和61(1986)年 | ・視聴覚室ができる。 |
| 昭和63(1988)年 |
・体育館・プールのできあがった記念の式典が行われる。 ・校庭の整備も行われ、スプリンクラーもできる。 |
| 平成5(1993)年 |
・うら庭に学年別のさい園が、ととのう。 ・創立120周年のお祝いをする。 |
| 平成11(1999)年 | ・4年生宿泊体験学習が始まる。 |
| 平成12(2000)年 | ・総合的な学習の時間として「金沢タイム」が始まる。 |
| 平成13(2001)年 |
・はまっ子ふれあいスクールが始まる。 |
| 平成14(2002)年 | ・学校週5日制が完全実施される。 |
| 平成15(2003)年 | ・創立130周年のお祝いをする。 |
| 平成21(2009)年 | ・各学級にデジタルテレビが配当される。 |
| 平成23(2011)年 | ・各学級にエアコンが取り付けられる。 |
| 平成25(2013)年 |
・創立140周年のお祝いをする。 |