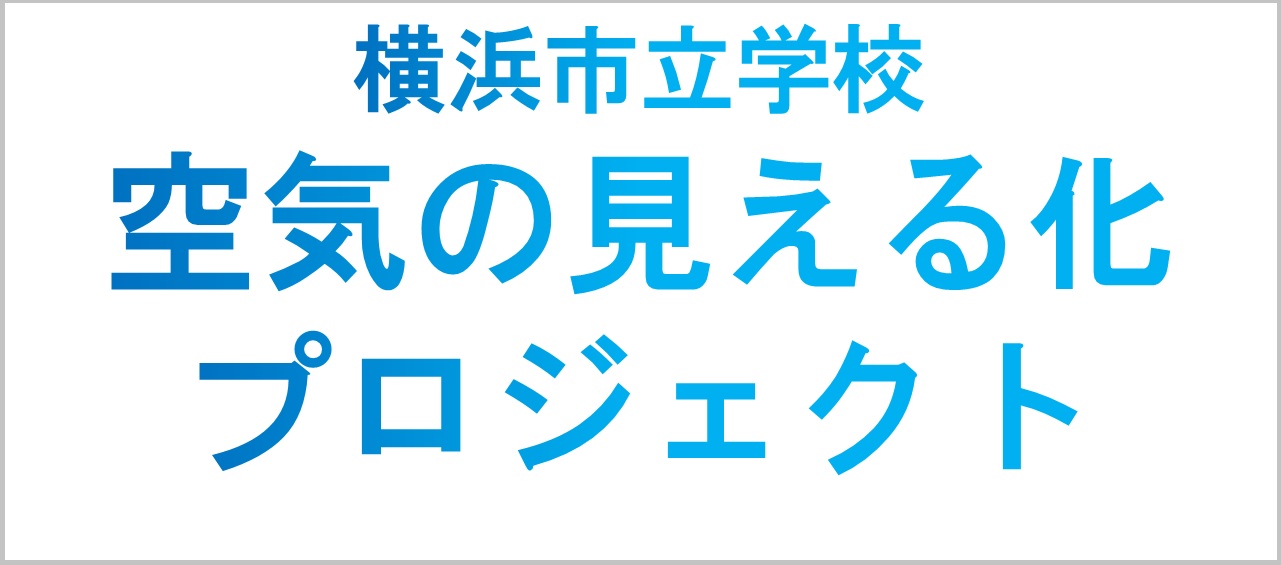校歌・校章
校歌
作詞:森 林太郎 (鷗外) 作曲:小松 耕輔 1916年(大正5年)制定
1番
栄行く御代の 民草我等
事業こそは 種々かはれ
かはらぬものは 心の誠
誠を守る 商人我等
いでや見ませ 朝な夕な
撓まず共に いそしむ我等
2番
競ひの場の ますらを我等
命のかぎり 人には負けじ
忘れむ家を 惜まじ身をも
力を頼む 商人我等
いでや見ませ 朝な夕な
撓まず共に 戦ふ我等
作詞した森 鷗外(本名:林太郎)について
1862年(文久2年)2月17日 - 1922年(大正11年)7月9日
明治-大正期の夏目漱石と並び称せられる小説家。
ただし、小説家はあくまでも副業で、本業は軍医(軍医の最高位である陸軍軍医総監まで務めた)。
処女作の『舞姫』をはじめ『雁』『山椒大夫』『高瀬舟』など多数ある。 また、『即興詩人』(アンデルセン作)『ファウスト』(ゲーテ作)などの翻訳でも有名。
Y校の校歌を作詞したと思われる1916年(大正5年)は、後に鷗外の最高傑作と評価される『澁江抽齋』の新聞連載を開始した年でもある。
ちなみに、妹の貴美子は、ショートショートで有名な作家、星新一の祖母にあたり、鷗外の娘、森茉莉も作家となるなど、家系には文筆で名を成したものが多い。
作曲した小松 耕輔について
1884年(明治17年)12月14日 - 1966年(昭和41年)2月3日
明治-昭和期の作曲家,教育家,評論家。
『母』(作詞:竹久夢二),『芭蕉』(作詞:北原白秋)などを作曲し、本居長世(『赤い靴』など)や中山晋平(『波浮の港』など)と並んで童謡運動の先駆け。
日本最初のオペラ『羽衣』(明治39)を作曲した。その際,楽譜の序文を森鷗外に依頼し、源高湛(みなもとたかしづ)というペンネームで書いてもらっている。
また、Y校の校歌を作曲したと思われる1916年(大正5年)の翌年には、やはり森鷗外の『沙羅の木』を作曲している。
なお、彼の書いた『音楽の花ひらく頃 ― わが思い出の楽壇 ― 』(音楽之友社 1952)は, 明治から大正期の日本における西洋音楽事情を知る上での貴重な資料となっている。
校章