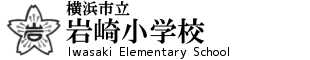学校教育目標
学校教育目標 『ひとがすき まちがすき いわさきの子』
(知)ともに学び合い、ねばり強く解決していける「考える力」を育てます。〈理性〉
(徳)自分も友だちも大切にし、「心豊かに生きようとする心」を育てます。〈人間性〉
(体)心と体の健康に関心をもち、「自分から行動しようとする力」を育てます。〈自主性〉
(公)異学年や地域と豊かに関わり、「人のために役立とうとする意志」を育てます。〈社会性〉
(開)日本や世界の文化や歴史を学び、「社会の変化や世界への関心」を育てます。〈国際性〉
登録日: / 更新日: