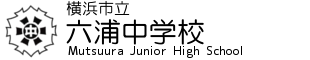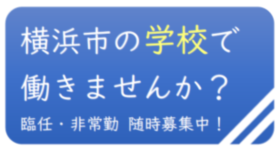学校長あいさつ
学校長あいさつ
2025 ご 挨 拶
校長 小宮 昌志
六浦中学校の校長として2年目になりました小宮 昌志(こみや まさし)です。生徒、保護者、地域の皆様、本年度も引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
毎朝、校門で交通安全の確認を行っていると、進んで挨拶をしてくれる生徒がいます。これまで保護者や地域の皆様に大切に育てられてきたことを実感し、皆様に感謝するとともに、大きな責任も感じております。本年度も校長として子どもたちの成長をしっかり支援していくことができますよう努力してまいりたいと思います。
本校の学校教育目標は次の3つです。
・自ら学び粘り強く学習する態度を育て、基礎学力の定着をめざします。(知)
・誰もが安心して豊かに生活できる、挨拶と笑顔のあふれる学校をつくります。(徳・体・公)
・積極的に社会参加し、地域の人達との関わりを大切にする心を育てます。(公・開)
本年度も学校教育目標の実現に向けて教育課程を編成し、六浦中学校の生徒が将来力強く生きていくために必要な力を身に付けられるよう職員一同、精一杯取り組んでまいりたいと思います。
本校の教育課程のベースは人権教育です。「誰もが安心して豊かに生活できる学校」を目指し、目の前の生徒をしっかり理解することに力を入れています。生徒一人ひとりが自分を大切にし、互いの違いを認めながら成長できることを目指しています。それぞれが目指す自分づくりを支えるために、自尊感情を育む授業や環境づくり、仲間や大人と関わる機会を大事にします。
授業の中で「できそうだ」とか「わかった」等と感じられることが自尊感情につながります。そのためには生徒自身が授業の見通しがもて、何を身に付けたかを振り返れるようにします。また自分の学習状況を理解して次の一歩を踏み出せるように、声掛けや対話や支援に力を入れていきます。その一つとして、令和5年度より、AIドリルを導入しました。今まで以上に自分に合った課題に自分のペースで取り組めるようになりました。機を同じくして、横浜市の学力・学習状況調査が大きく変わりました。点数で全体の中の位置を返すにとどまっていたところから進化し、学力の変容や伸びの状況を個別に詳しく分析する仕組みになりました。そのデータも授業づくりや生徒の理解に有効活用します。
教科以外の学習は、教科の学びを支える力を育てます。これまで通りに学級活動や生徒会活動、学校行事や部活動など、協働的で体験的な活動を重視します。部活動では昨年度から部活動指導員と教員が一緒に顧問を務める形になりました。一部活動当りの顧問数が増えたことで、より持続可能な体制となりました。
引き続き「アットホームスタディ」と「校内ハートフル」にも取り組み、個別最適な学びを保障します。学校に登校できない場合等で学校が認める時は、家庭で学習できるよう授業のLIVE配信を行います。そのために教室にはプロジェクターを設置しました。校内ハートフルルームには、支援員が1名常駐するとともに、全職員で支援することによって、より多くの生徒の学びの保証や居場所となるようにします。
人と人の温かい関わりを重視するのと同じくらいにICT活用能力の育成も欠かせません。ICTを使ってコミュニケーションする力が将来はさらに強く求められるでしょう。ICTを使って多様な人と一緒に課題を解決していく力を身に付けることが学校の役割の一つです。その力を育む風土を醸成するために、様々な教育活動や保護者等との連携にもICTを積極的に取り入れます。変革期にはトライ&エラーがつきものですが、臆せず前向きに、そして改善を重ねながら取り組んでまいります。
本年度も『横浜市教育振興基本計画』 に基づき、全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現にむけた教育課程を展開します。また、職員の働き方改革と適切な経理についてもさらに進めてまいります。皆様には本校の教育課程へのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。