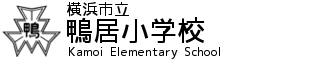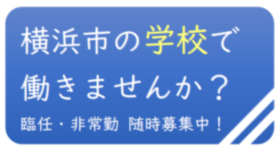学校だより
![]() 3月号
3月号 ![]() 2月号
2月号 ![]() 1月号
1月号 ![]() 12月号
12月号 ![]() 11月号
11月号 ![]() 10月号
10月号 ![]() 8・9月号
8・9月号 ![]() 7月号
7月号 ![]() 6月号
6月号 ![]() 5月号
5月号 ![]() 4月号
4月号
【2月号巻頭言】
学校教育と“動的平衡”
校長 角皆 裕文
3月に入り、各学年がまとめの学習に取り組み、進級や進学を意識しながら日々を過ごしています。どの月も時間の流れは同じはずですが、3月の日々にはやはり特別な思いが宿ります。長かった小学校生活を終えようとしている6年生をはじめ、1年間ともに学んできた仲間と過ごす特別な数日間を丁寧に見守ってまいります。
保護者の皆さま、地域の皆さまにおかれましては、この一年間のご支援とご協力に厚く御礼申し上げます。
「学校はただの箱なのだな」
私が教員として働きだしてすぐ、ぼんやりとそんなことを思ったのを覚えています。毎年まとまった数の子どもが入っては出て、大人も入っては出ていく。それなのに、建物はもとより、組織、慣習、前例といった「箱」の形はなかなか変わりません。カリキュラム編成の拠り所となる学習指導要領はおよそ10年ごとに変わりますが、「箱」が変わらないために、国がねらうような変化がなかなか起きないのが現状です。
なぜ箱の形は変わらないのか。理由はいくつかあると思いますが、大きな理由のひとつは「中の人は通り過ぎていくだけ」だからではないでしょうか。数年で出ていくのがわかっているのに、わざわざ箱の形を変えようと思う人が少ないのはよくわかります。また、次の人へ引き継ぐことを考えると、形を変えることをためらう気持ちもよくわかります。しかしながら、社会は変わっていくのに、目の前の子はすぐに通り過ぎてしまうのに、それでいいのでしょうか。
人間も含め、生物は常に同じような姿をしているように見えるが、環境に適応するために日々細胞が入れ替わっている。さらには、物は時間が経てば劣化してくのが当然だが、生物は壊れる前にわざと自らの一部を壊し、新たなバランスで作り直すことによって崩壊を逃れている
この生物のしくみを生物学者の福岡伸一氏は「動的平衡」という概念で捉えています。
自らを壊し、変わり続けることで環境に適応していく必要があるのは、まさに学校教育も同じだと言えます。AIとの共存、不登校児童35万人、多様化する教育ニーズ・・周りを見渡せば、学校教育が変わらなくてよい理由はありません。
たとえ鴨居小学校を通り過ぎていく身であったとしても、目の前の子ども達のために「今できること」をしようと私たちは挑戦を続けます。学校が伴走できるのは、ほんの限られた時間にすぎません。子ども達が学校を卒業しても、自ら問いを立て、学び続ける人になってほしい。その願いを込めて日々変化していく鴨居小学校を来年度も見守っていただければ幸いです。