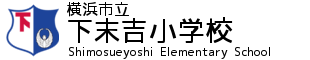更新情報
-
この日の1・2校時に4月入学予定の園児を招いて、新1年生と遊ぶ会を開きました。
前半はいくつかのグループに分かれて、1年生が校内を案内しました。
「発表する順番に並んだらどうだろう」と提案したり、必要なことをあらかじめメモして準備したりしている1年生もいました。
また教室では、生活科での作品を紹介したり、急遽、iPad保管庫を見せたりと、日頃の学習の様子を上手に伝えていました。



後半は体育館で交流会を行いました。
交流会には5年生も合流し、学校についての○×クイズやじゃんけん列車を楽しみました。
1年生と5年生は、特に新1年生と多く関わる学年です。
新1年生が下小に親しんでもらうとともに、来年度に向けて在校生も親しむきっかけとなった遊ぶ会となりました。
-
この日の放課後、学級の代表やPTAの方も参加して第2回学校保健委員会を行いました。
最初に各学級の代表が、前回の学校保健委員会を受けて取り組んだことと振り返りを発表しました。
次に、健康委員会より、全校アンケートの結果を報告しました。


後半はスクールカウンセラーから「心と体を整えるリラックスの技」として、正しい姿勢や呼吸法とリラックスの関係性についてお話しいただきました。
最後は、1年間の取り組みを振り返りつつ、正しい姿勢やリラックスについて話し合いました。
感想交流では、姿勢が健康に影響を与えることに驚いたり、学級や家庭でも姿勢チェックをやってみたいという話が出ました。


今回はリラックスの観点から姿勢や呼吸法について考えました。
近年ではリラックスにより身体や脳機能が向上することも分かっています。
今年度取り組んだことを振り返り、生かしながら学校生活を過ごせることに期待します。
-
この週の火曜日と木曜日に、本年度最後の交際理解教室を行いました。
今回はインドネシアの伝統的な遊びを体験しました。
Gasing(ガシン)は竹でできたコマです。




最初は上手に回せずにいましたが、しばらくするとコマ回し大会ができるまでに上達しました。
Gasingは速く回ると笛のように音が鳴る仕組みになっています。
安定して回るようになったGasingが出す音に、静かに耳を傾ける一幕もありました。
Bekel(ベコー)は、投げたボールをキャッチする間に、床に置かれた貝をできるだけたくさん取る遊びです。



子どもたちは、投げたボールと貝を取る動きを同時に行う難しさに歓声を上げていました。
そして木曜日の昼にzoomでお別れ会を行いました。
代表の子どもからお礼の言葉と花束の贈呈がありました。


この1年間、インドネシアの太陽のように明るく元気なセプティヤンティ先生と楽しくインドネシアの文化を学ぶことができました。
これからも子どもたちが様々な文化に関心をもてるよう、多文化理解学習を進めていきたいと思います。
Terima kasih. Sampai jumpa lagi.(テリマ カシ、サンパイ ジュンパ ラギ)
-
この日の2校時は、末吉にこにこ保育園の年長さんが来校し、1年生と交流会をもちました。
1年生は、楽しく過ごしてもらえるように、様々な遊びを準備しました。
また、やっていることが分かるように看板を作るなど、相手のことを考えて交流会を迎えました。




当日はあいさつの後、早速交流開始です。
最初は固まって行動していた年長さんも、慣れるにしたがって自分の楽しみたい遊びを選んで交流していました。
1年生もだんだん声掛けが自然になり、用意していた遊びから広がった新たな遊びで交流する子もいました。
近年では幼稚園や保育園から小学校への学びの連続性が重要視されています。
年長さんには小学校のイメージをもってもらうこと、1年生は生活科などでの学びを生かす場として、今後も幼保小の交流を図っていきたいと思います。
-
この日の朝は、体育館で「6年生を忘れないビンゴ」集会を開きました。
最初に、6年生に関するキーワードの中から、グループで選んでビンゴカードを作りました。




そして、いよいよビンゴ開始です。
ステージ上で集会委員会の6年生がくじを引きながら、ゲームが進んでいきます。
今回のビンゴでは、なんと3つめのワードでビンゴ達成のグループが現れました。
これには会場が盛り上がり、その後もビンゴになったことを知らせるグループが続きました。
最後は6年生の列の間を下級生がハイタッチしながら楽しそうに通り抜けて教室へ戻っていきました。
ビンゴを通して、6年生についてみんなで考え、もう一度理解を深める良い機会となった集会でした。
-
学校図書館では季節や学習に合わせて、蔵書や学習資料の紹介を行っています。
この日は節分でしたので、節分や鬼をテーマにした蔵書の紹介をしています。
そして、年間を通して年代やテーマ別でも本の紹介をしています。


また、学校司書が子どもたちの学習に関連する図書を選んで準備や紹介をしています。
現在、学校図書館の入口には、5年生が国語科で取り組んだお気に入りの詩が紹介されています。
図書館内には3年生一人ひとりがおすすめする民話、4年生からは各々お気に入りの詩を集めた詩集などが展示されています。



読書離れが心配される昨今ですが、引き続き本校の学校図書館の利用は盛んです。
今後も、文化と学びの場として学校図書館の活用を推進していきたいと思います。
-
暦の上でも2月に入り、明後日に立春を迎えます。
校舎前の梅の木は一足先に桃色の花をつけています。


今シーズンの横浜は観測史上最速で梅が開花したそうです。
それでも空渡る風は、未だ木枯らしです。

さて、この梅の木は本校創立30周年を記念して植樹されたものです。
長年の風雨に耐えながら、今年も花を咲かせました。
この木を植えた人たちに思いをはせながら、引き続き学びに勤しみたいと思います。
-
この日の2校時は、外部の講師をお招きし、2年生がソプラノリコーダーの演奏の仕方を学びました。
リコーダー演奏では、「姿勢」「指遣い」「息の強さ」「タンギング」が重要であることを知り、一つずつポイントを確認しながら学んでいきました。


そして、今日学んだ「シ」の音だけで構成されている「笛星人」の演奏を聴き、全員でチャレンジしました。
また、他の種類のリコーダーも見せてもらいながら、楽器の特徴も学びました。
ソプラノリコーダーの学習は3年生から本格的に始まります。その後も5年生からはアルトリコーダー、中学校では篠笛の演奏も学んでいきます。
吹いて音を出す管楽器では、特に息遣いが音色を左右します。
音を出すのは簡単、きれいな音を奏でるには練習が必要。
そんなリコーダーを極めた「笛星人」を目指して、音楽を楽しんでいきたいと思います。
-
この日の朝は音楽集会でした。
1年生が歌と楽器を合わせて「フルーツケーキ」を、手話を交えて「さんぽ」を歌いました。




1曲目のフルーツケーキは、2番と3番の歌詞を自分たちで工夫したものを歌いました。
2曲目のさんぽでは、手話を交えながら動きのある表現ができました。

感想交流では、上級生が1年生らしい表現の良さについて伝えることができました。


最後は、今月の歌「パプリカ」を全校で歌いました。1年生は振付と合わせて歌っていました。
1年生にとっては、音楽集会で初めての披露となりました。
緊張の中に、自分たちの成長を表現することができた音楽集会でした。
-
この日はペア学年によるなかよし給食を実施しました。
まず中休みに、給食クイズ大会が開かれました。
健康委員会が作成したクイズを早押し形式で8問答えるものです。
正解の他に、早押しの順番も表示され、楽しみながら給食について学びました。




そしていよいよなかよし給食の始まりです。
いつもと異なる人と給食を食べることで、より和やかな雰囲気で給食を楽しみました。




最後は給食ビンゴです。
事前に好きな給食についてアンケートを取り、それをもとにビンゴをしました。
子どもたちは次に出てくるものを話し合いながら、盛り上がることができました。




この日の給食では、食事を楽しむだけではなく、苦手なものもいつもより頑張って食べようとする様子も見られました。
雰囲気を変え、楽しみながらも食べることにも取り組めたなかよし給食でした。