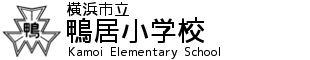学校だより
【7月号巻頭言】
「宿泊行事」を考える
校長 角皆 裕文
梅雨の最中に思いがけない晴天に恵まれ、5,6年生が宿泊行事を終えました。5年生は家庭科で繰り返した実習を活かし、美味しいカレーを作ることができたようです。私が同行した6年生の修学旅行では、グループ活動の中で互いを思いやって声をかけたり、進んで5分前行動を試みたりと「よい集団」になろうとする意欲が見られ、とても頼もしく思いました。
修学旅行の歴史を調べてみると、その原型が東京師範学校で始まったのが明治19年。当初は軍事教練の要素が色濃く、その後博物、史跡名所の見学が加わり、最終的に軍事教練が分離され、観光の要素の強い現在の修学旅行のかたちが定着。時を経てそれが小学校にも広がっていったようです。平成に入り、“体験型”の修学旅行へシフトする動きも見られましたが、今も横浜市の多くの6年生が栃木県日光市に出かけていることからすると、当時に確立した修学旅行の性格がそのまま残っていると言えそうです。
現行の学習指導要領には、「遠足・集団宿泊的行事」としてねらいが次のように書かれています。
「自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあって,見聞を広め,自然や文化などに親しむとともに,よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができるようにすること。」
“宿泊的”という言葉が表すように、必ずしも宿泊することを前提とはしていません。
さて、子ども達が楽しみにし、貴重な経験を得られる宿泊行事ですが、これを続けようとするならば、私は本校の職員および児童の人権を尊重する立場として、次の課題と向き合わなければなりません。
■長時間労働の問題
子どもを引率している限り、職員は休憩を取ることはできません。子どもの就寝時間を過ぎたあと、打ち合わせを行い、入浴したあとも部屋を見回り、起きている児童に声をかけたり、室温を確認したりします。例え睡眠が取れたとしても、子どもに何かがあれば起きて対応しなければならない時間は「休憩時間」ではなく、使用者の指揮命令下に置かれている「労働時間」と言えます。つまり、1泊旅行の引率をする職員は40時間近く働き続けることになります。
■時間外手当の不支給
労働基準法は1日8時間を超えた労働については「割増賃金」の支払いが義務付けられていますが、「給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)」が適用されている教員には残業代が支給されず、当然深夜労働手当も付きません。宿泊行事の引率については「特殊勤務手当」として1日4,000円が支給されるに過ぎません。
交通費および宿泊費用については支給されますが、食事代については1泊につき朝・夕2食まで。昼食代は日当でまかなうことになりますが、行き先が県内であれば日当はつかず、残りは職員の持ち出しとなります。
■下見の方法の制限
学校として毎年訪れている場所であっても下見は必要です。公用車として登録した自家用車があれば利用できますが、燃料代として1kmあたり37円が支給されるにとどまります。それ以外は原則として公共交通機関(公費負担)を使用することになっており、交通手段の乏しい地域で数ヶ所を回るためには、数万円(公費負担)をかけてタクシーを一日借り上げる必要があります。
また、子どもの登校する日に学年の職員が下見に行くのは実際不可能なので、学年立ち上げで忙しい4月2日~4日あたりに行くしかありません。それ以外となると休日に行かざるを得なくなり、厳しい制限をクリアできず「完全ボランティア」で行くケースすらあります。
そうまでして下見に行こうとするのは、行かずに万が一子どもが事故にあった場合、安全配慮義務違反を厳しく問われることになるからです。
■子どもの人権について
日本国内のLGBTQの割合は8.9%と言われ、80人の学年であれば7人存在することになります。男女別の部屋で寝かせたり、お風呂に一緒に入らせたりすることが、自らの性に違和感をもつ子らを苦しめてはいないか、とても気になります。
このように学校教育においては、発祥したときの時代背景やねらいが忘れられ、形だけが残り続けている活動が多くあります。「子どものため」と掲げられると、思考が止まってしまいがちなのは私たち教員の欠点でもありますが、一労働者としての尊厳を大切にし、子ども達の眼に「魅力的な職業人」として正しく映ることこそが、教員のなり手を増やし、ひいては未来の教育を豊かにしていくのだと信じているのです。
「宿泊行事」について、みなさんのご意見をお聞かせください
■「宿泊行事」を考える(Googleフォーム)
https://forms.gle/u7y9poZcfDW4wxoX7