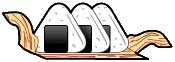
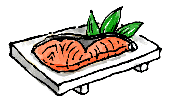

1月24日をはさむ1週間を給食週間とし,日ごろなにげなく食べている給食にかんしんをもち,しょくじについて学ぶいろいろなかつどうが行われています。
学校給食の歴史
明治22年 山形県鶴岡町の忠愛小学校(お寺)で,お弁当を持ってくることのできない子どもたちのために,おにぎりとおかず(さけ・つけもの)の昼食を出したのが学校給食のはじまりです。
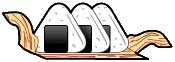
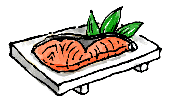

昭和7年 学校にこられない子や,体の弱い子をすくうために,全国各地で給食がはじまりました。
昭和19年 戦争で食べ物が少なくなって,米・みそなどのとくべつ配給の学校給食がじっしされました。(六大都市)
昭和21年12月24日 外国からおくられたミルクやかんづめで,学校給食がはじまりました。給食記念日は12月24日になるところですが,冬休みにはいってしまうので,1ヶ月後の1月24日を給食記念日とするようになりました。
~横浜市の学校給食の歴史~
| 昭和21年12月 | 鶴見区の岸谷小学校で給食がはじまりました。 |
|---|---|
| 昭和22年ごろ | みそしるかすましじる・脱脂粉乳(だっしふんにゅう)の給食でした。 |
| 昭和26年ごろ | 週3~5日,コッペパン,みそしる,脱脂粉乳(だっしふんにゅう)などの,「パン,ミルク,おかず」のそろった「完全給食」がはじまりました。 このころの給食のようすのしゃしんへ |
| 昭和31年ごろ | パン,マーガリンやジャム,脱脂粉乳(だっしふんにゅう),おかず(しるもの,にもの)など,給食にいろいろなものが出るようになりました。 |
| 昭和41年ごろ | |
| 昭和52年ごろ | びんいりの牛乳から紙ようきいりの牛乳になりました。 |
| 昭和56年 |  ごはんがこんだてにとりいれられました。 ごはんがこんだてにとりいれられました。 |
| 平成1年ごろ | ごはんが週に2回になり,魚をつかったこんだてもふえました。 |
| 平成12年度 | ①卵アレルギーの児童があんしんしてたべられるように,フライやハンバーグなどの加工食品に卵をつかわないことになりました。
②ソーセージやハムに入っている発色剤(はっしょくざい)は店で売っている物の1/5の量でしたが,無添加(むてんか)の物を使うようにしました。 |
| 平成13年度 | ①遺伝子(いでんし)組み替え(くみかえ)食品(しょくひん)を使わないというもくてきで米の油をつかうことになりました。
②パンの種類がふえました(くろしょくパン,8mmチーズパン,バターブレッド,ツイストロールパン) |
| 平成14年度 | ①ごはんの回数が週2回から2週で5回(1週間に2.5回)になりました。
②主食(しゅしょく)のしゅるいがふえました(すめし,おせきはん,むぎごはん,ターメリックライス,はいがごはん,はい芽パン) ③日本でとれたこむぎこを20%ブレンドしたパンがとうじょうしました。(コッペパン,ドッグパン,まるパン,バンズパン,ねじりパン,ロールパン,サンドパン,ツイストロールパン) |
| 平成15年度 | 横浜でとれる野菜を使ったこんだてを小学生が考える、はま菜ちゃん料理コンクールが始まりました。 |
| 平成16年度 | はま菜ちゃん料理コンクール入賞作品「はま菜チャンプル」が初めて給食になりました。 |
| 平成21年度 | 横浜開港150周年記念、横浜市学校給食スペシャルメニューを作りました。
(はいが丸パン,牛乳,リヨン横濱(よこはま)風スープ,ポテトリヨネーズ,アイスクリーム) |
| 平成22年度 | 平成23年3月11日 東日本大震災が発生しました。学校給食も震災の影響を受けました。 |
| 平成25年度 | 給食を作っている小学校と特別支援学校は合わせて355校。1日約19万食を作っています。 |
| 平成29年度 | ①ごはんの回数が2週に5回から7回(1週間に3.5回)になりました。
②5月に横浜市の全小学校で「ベイスターズ青星寮カレー」が提供されました。 |
| 令和元年度 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、全国の学校が一斉臨時休業になりました。
横浜市の学校も令和2年3月3日から休業しました。 |
| 令和2年度 | 令和3年1月の「すきやき風煮」は、学校給食活用支援事業による神奈川県産等の和牛肉が使われました。 |
| 令和3年度 | 横浜市中央卸売市場本場と連携して、さばの未利用魚を令和4年2月に「さばのみぞれあんかけ」にしました。
未利用魚とは…魚のサイズがふぞろいだったり、とれた量が少なかったため食用にされなかったり、食用として売れても値段が低い魚のことです。 |
 食べものアイランドにもどる
食べものアイランドにもどる