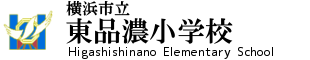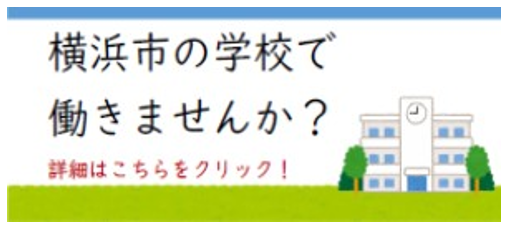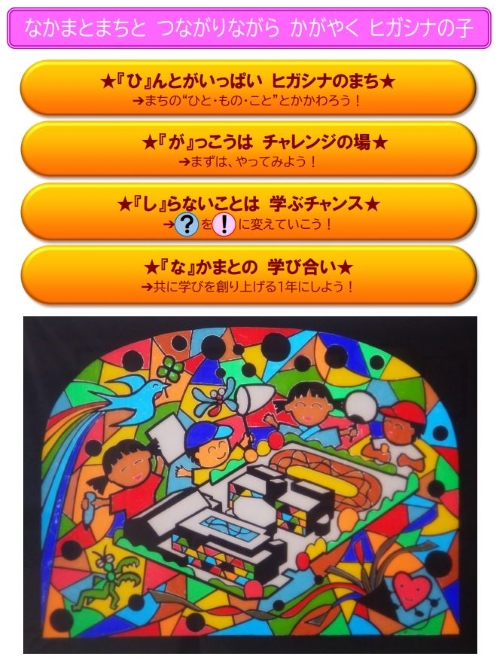更新情報
-
子どもたちがそわそわしているので話を聞いてみると、「これからレクが始まるんだ。」とのこと。しばらく見ていると、図書係の子どもたちが『おおきなかぼちゃ』という絵本の読み聞かせを始めました。1年生の時に おおきなかぶ というお話を勉強したので選んだそう。図書レンジャーの方々による読み聞かせをよく見ているため、ページのめくり方や話し方が上手でした。次は、遊び係の子どもたちによる『おにぎりゲーム』です。おにぎりゲームは、昨年度の樹木班活動の際に何度かやったことがあるため、子どもたちは歓声をあげながら取り組んでいました。今週ずっと子どもたちと過ごしてきた教育実習生も加わると、子どもたちの視線は黒板に釘付け。「○○先生、がんばって。」「まだいけるよ。」等の声援を受けながら、一緒に楽しむことができました。子どもたちにとっても良い思い出となったことと思います。これまでに体験したことを活用しながら自分たちの手で創り上げるレクを通して、様々なことを感じ、考えてほしいものですね。
-
本日の樹木活動は、掃除の時間から開始。6年生が1年生を迎えに行くと、にこにこ笑顔の1年生。1年生と手をつないだり、おしゃべりをしたりしながら、6年生の優しさが伝わってくる姿も見られました。集合教室への移動が終わると、樹木長(班のリーダー)を中心に6年生が声をかけながら、分担場所の掃除タイム。雑巾がけをしたり、一緒に机を運んだり、ドアレールの埃を取ったりと、素早く活動する樹木班もありました。掃除が終わると、集会タイム。班ごとに6年生が準備してきたゲームを楽しみました。王様ゲーム・じゃんけん列車・ワードウルフで、子どもたちの笑い声に包まれる心温まる時間を共有した子どもたち。1年生は、「楽しかった。またやりたい。」と嬉しそう。6年生にも話を聞いてみると、「楽しくできたけど、イメージしていた部分まではできなかった。静かに聴いてくれなかったり、ゲームの時間が足りなくなっちゃったりした。次は時間に気をつけて計画したい。」と話してくれる子もいました。こうした異学年交流を継続していくことで、相手を思いやったり活動を調整したりする“非認知能力”が育まれるのだと感じます。
-
『ちいちゃんのかげおくり』は、長い間教科書に掲載されている物語のため、保護者の皆さんも記憶に残っているかもしれません。教室では、3年生の子どもたちが何度も読み返しながら学んでいます。2組では、5行しかない第5場面の必要性について、自分の考えをノートに書き、クラス全体で話し合っていました。じっくりノートを見ると、「ちいちゃんは、天国で家族に出会えたはず。だから、5場面は必要だと思う。」「ちいちゃんが空から見てくれているから、安心して遊べるようになったということを伝えているし、もう二度と、ちいちゃんと同じ目にあいませんようにという願いがこめられているから、絶対に必要。」等の記述が。これまでの学びをもとに、ちいちゃんや家族の行動や気持ちを捉えた上で、情景をイメージしながら考え、作品に対する考えをもつことができました。ぜひ、お子さんの考えを聞いてみてください。
-
子どもたちが楽しみにしている図書の時間。図書館では、思い思いの場所で自分の好きなシリーズや初めて手にした本を読む姿は、エンゲージメント状態です。「校長先生、この本はね、ネズミやハムスターが出てくるの。このページが好きなんだ。」と言って、実際にページを開いて見せてくれました。また、「このシリーズは、もう9つ目。どれも楽しい。」「電車が好きだから、この本を選んだ。横須賀線が好き。南海の特急に乗ってみたい。」「おじいちゃんの本が面白かった。私のおじいちゃんに似ているところもあった。」などと話してくれ、豊かな感性がさらに磨かれているのを感じました。最後には、学校司書のところへ本を持っていき、本を借りる子もたくさんいました。本離れがニュースになる時代ですが、小学校段階では、実際に本の表紙の絵を見比べたり、ページをめくってみたりしながら興味のある本を自ら選び、何度もページを行き来しながら読む体験が重要だと思います。これからも、本に親しむヒガシナの子であってほしいと願っています。
-
同じ時間に教室に行ってみると…。みんなが同じ問題について考えるのではなく、一人一人が自分の課題にじっくり向き合い、自分のペースで真剣に学んでいました。しばらく見ていると、ある教室では音楽交流会へ向けた練習中。リコーダー奏を練習している高学年の子の様子を見ながら、リズムを感じ取っている低学年の子は、耳に残っているリズムを大切にしながら鍵盤ハーモニカの練習を頑張っていました。「リコーダーは、ファの音の指づかいが難しいんです。」「○○さんは、とっても上手。」等、和気藹々とした雰囲気が素敵です。別の教室では、低学年の子たちが水のかさを学んでいました。『底面積が違うものの高さの同じ2つのペットボトルに色水を入れるとどうなるか』について、実際に色水を入れる活動を通して発見することができたようです。「細い方が早くいっぱいになっちゃうってことは、量が少ないんだ。太い方がお得。」と呟く場面も。実生活と関連させながら学んでいるようですね。さらに別の教室では、ヒガシナタイムの時間。静かな教室で、友達の素敵なエピソードを付箋に書く真剣な眼差しと鉛筆の音が印象的でした。ホワイトボードに貼って仲間分けし、『楽しい』『やさしい』『かっこいい』『親切』等に整理することができました。今後が楽しみです。
-
6年生の子どもたちも集中して学んでいます。1組では、拡大図や縮図の学習。角の大きさや辺の長さの比が等しいという法則をもとに、練習問題に取り組んでいました。「図形は苦手だから、ちょっと大変だけど、比が分かると簡単に解ける。」と話してくれました。2組は音楽室で合奏の練習。情熱大陸のテーマ曲を様々な楽器に分かれて練習し、みんなで合わせてみると、「あっ、ここが難しい。自分のパートだけだとできるんだけど、他の楽器のパートが入ると、タイミングを合わせるのが難しい。」と呟いていました。3組は理科室で顕微鏡を覗く姿が。ヒガシナ広場の池やプールから採取した水を観察し、どんな微生物がいるのか見合っていました。「おっ、すごい。心臓かな。動いている。」「これは、緑藻の仲間かな。」などの歓声が聞こえてきました。引き続き、『ひ・が・し・な』を目指してほしいと願っています。
-
子どもたちの想像力には驚かされます。1組の図工では、『ふしぎなたまご』のイメージを膨らませながら作品作りに没頭中。色や形、割れる場所や中から出てくるものを考えている子どもたちは、うきうきした表情です。「見て見て。これはギザギザの世界なんだ。たまごを割ると、こんな風にギザギザが広がる。」「卵から宇宙が飛び出すんだ。星がきれいなの。」など、夢は広がる一方です。2組の国語は、『あったらいいな』と思うもののイメージを膨らませながら、自分のアイディアを整理していました。何枚もの設計図?のようなシートに描いたデザイン案をもとに、最終的な『あったらいいな』と思うものを描く姿は真剣。「ぼくはね、どんな物でも軽く感じる装置のことを書いたんだ。そうすれば、買い物をした時にも便利だから。」「おにぎりマシーンがあったらいいな。食べたいおにぎりをすぐ作ってもらえたら、みんな喜ぶから。私は鮭を作ってほしい。」等、嬉しそうに教えてくれました。一人一人の思いを広げ、ダイナミックに表現する子どもたちの豊かな感性が素敵です。
-
昨日の朝会で3か月ぶりに富士山が見えたことを話したところ、低学年の子どもたちが早速学校の中を探検していました。さて、5年生の教室では、子どもたちが活発に活動しています。1組では、ヒガシナタイムの話し合い。早い時期から活動がスタートしているため、数人で作っていた『ごのいちスイッチ』の装置をつないでいくためにはどうしたらよいかという点について意見が出ていまし「鉄でできたレールだと安定するから修正したい。」「ジップラインは、プラスチックのコップの方が安定すると思う。」等、新たな?を!にしていくために知恵を出し合っている姿が素晴らしいですね。2組では、四角形の内角の和は何度かという問いについてグループで考えていました。三角形2つに分割し、既習事項である“三角形の内角の和=180度”の2つ分だから360度になると考えたグループ、向かい合った頂点同士に対角線を引いて4つの三角形に分割し、180度の4つ分から対角線が交わる部分の360度を引いて考えたグループと様々。実際に図形を操作しながら、体験を通して学ぶことが重要ですね。3組は、これまでに読んだ本のキャッチコピーを考える時間。アガサ・クリスティーの本を読んだ子に聞いてみたところ、「読んだ2冊は、どっちも推理しながら読んだ。だから、『あなたは、この謎を解けるか?』っていうのはどうかなって考えている。」と話してくれました。さあ、どんなキャッチコピーが出来上がるのか、楽しみです。
-
3か月ぶりに富士山がくっきりと見えた朝。ツクツクボウシの鳴き声と僅かではありますが涼しい風に夏の終わりを感じ取ったものの、すぐに猛暑が復活してきました。教室では3年生の子どもたちは気持ちを切り替えて学んでいます。1組はずっと育てている植物の観察タイム。実物をよく見ながら色・大きさ・匂い等を熱心に観察し、カードに記録していました。花の真ん中の部分が濃い紫色になっていると書いてあるので、何か理由があるのか聞いてみると、「うーん。もしかしたら、花の真ん中が目立つから、虫が寄ってくるようにしているのかも。」と、素敵な予想が。新たな?が生まれた瞬間ですね。2組はローマ字の学習。表を見ながら、こくご・しゃかい・さんすう…と、教科名を打つ表情は真剣です。話を聞いてみると、「しゃかいの小さい“ゃ”が難しい。」とのこと。子音を重ねて打つことを覚え、頑張って練習する姿が印象的です。3組は図工。ダンボールに穴を開け、思わず顔を出したくなるパネル作りに取り組んでいる様子。友達と協力しながらダンボールカッターで自分の顔のサイズに穴を開けながら、どんなパネルにしようかアイディアを膨らませている子どもたち。こちらもワクワクしてきますね。
-
4年生の教室に行ってみると、1組では算数。『60枚の色紙を1人に20枚ずつ分けると何人に分けられるか』という問題の解き方を考えていました。これまでのように60個の丸を描き、20個ずつ線で囲っていくことをイメージすると…「時間がかかりすぎちゃう。」「10のまとまりをもとに考えれば、全部で6つ。20枚は10のまとまりが2つだから、そのまとまりが3つできる。」等、積極的に意見を述べる姿が見られました。2組は音楽。チキチキバンバンを鍵盤ハーモニカで熱心に練習していました。「フラットがあるから、黒いところ(黒鍵)を弾くのが難しい。」「速くなるところが、まだできない。もっと練習しなきゃ。」との声。鍵盤ハーモニカのため、タンギングにも気を配りながら練習を重ねるうちに、素敵な音色になってきたように思います。3組では、外国語活動。“What season do you like ?” “I like ~.” “Why?” “Because, I like~.” という会話。“I like spring.” “Because, I like cherry blossom.”と、AETと英語でのコミュニケーションを楽しむ場面が微笑ましいです。